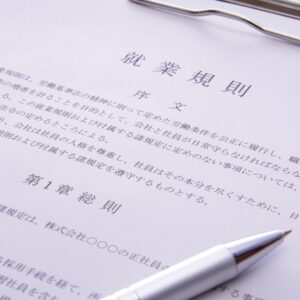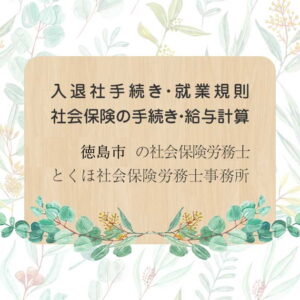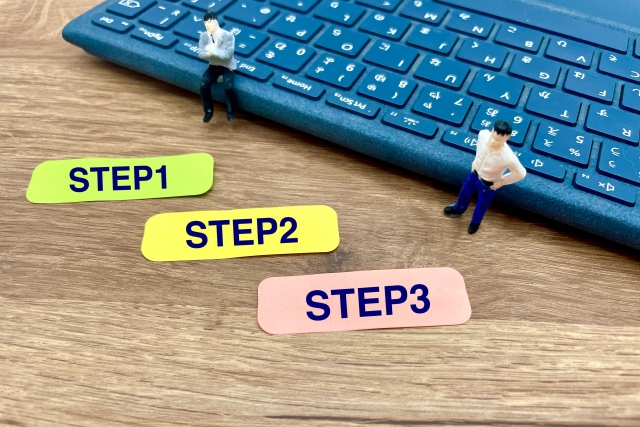

「ハラスメント対策は難しい」――この言葉は、もう20年以上前から、職場の現場でも、専門家の間でも言われ続けています。
現代のハラスメントは、身体的な暴力のような「分かりやすい」相談は減り、精神的な攻撃や個の侵害を広めに解釈した、複雑な事例が主流です。
何がハラスメントにあたるか、単純な線引きはできず、経営者や管理職の方にとっては、なおさら判断が難しいテーマでしょう。
この記事では、今、社労士として、難しいテーマにどのように取り組んでいるか、メモ代わりに残しておきたいと思います。
複雑化するハラスメントの現状:「分かりやすい暴力」から「精神的な攻撃」へ
一例として、パワーハラスメントの六類型(パワハラ6類型)は以下の通りです。
・身体的な攻撃
・精神的な攻撃
・過大な要求
・過小な要求
・人間関係からの切り離し
・個の侵害
ただ、昨今私達が受けるご相談の多くは「分かりやすい」身体的暴力や暴言ではありません。
受け取った側が「精神的な攻撃」や、「個の侵害」を広く解釈していて、上司や同僚からすると「雑談」や「業務上の注意」の範疇だと認識していたような事例も多いです。
コンプライアンスに気をつけたいがゆえに、部下とのコミュニケーションにビクビクし、コミュニケーション不全に陥ってしまう経営者、管理職の方も多く見られます。
一方で、残業代を払わないとか育児休業の取得を拒否するといった明らかな法律違反をしている経営者が「最近はなんでもハラスメントだ」と嘆くケースもあり、コンプライアンス意識の差が広がっている感じもします。
(悪気がない場合が多く、知識がないだけなので、法違反についてはリスクを踏まえて優しく助言するように努めています)
裁判が示す傾向と「人間関係頼み」の限界
「難しい」と言われる原因の多くは、受け取る側の状況や感じ方によって、訴えられるかどうかも、裁判の判決も変わるという点にあります。
単純な白黒では説明できない、曖昧な部分が多いのです。
実務的な判断を下すにあたり、私たちは裁判の判決、いわゆる「判例」を勉強し、ハラスメントの線引きのヒントを探ります。
(時代背景が違う場合もあるので、判例を鵜呑みにしてはいけないことは考慮に入れつつ)
これまでの事例から「人格攻撃」や「従業員の落ち度や悪い点を不必要に周囲へ知らせる行為」は、指導の枠を超えてハラスメントと判断されやすい傾向があることがわかっています。
例えば、人前での執拗な叱責や、業務に無関係な課員全員をCCに入れて当事者を貶めるようなメールなどがこれにあたります。
【関連記事】上司として気をつけたい「パワハラ」 指導とハラスメントの境目は?
上記の記事でも紹介したように「普段の人間関係」や「職場との信頼関係」により、裁判の判決が変わってしまう事例もあり、線引きは難しいです。
弁護士さんの研修でのアドバイスも「普段から部下が相談に来てくれたり、部下に対して率直に謝れる関係なら大丈夫」といった、人間関係ベースの「安心感」頼みになりがちです。

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所・入退社手続き・就業規則・社会保険の手続き・給与計算をサポートのイメージ
専門家としての知識や感性のアップデート
ハラスメント対応は、まだ判例も出揃っておらず、実務的な判断が難しい分野です。
だからといって「難しいから」と遠ざけるわけにはいかず、私たち社労士が、一緒になって「難しいですよねえ」と愚痴をこぼしていては「専門家の意味とは?」と問われてしまいます。
私達には法律の知識だけでなく、数多くの事例を見聞きし勉強する機会があり、伝えられることもあるはずです。
「ハラスメントの意図はないし、客観的に見てもハラスメントとは言い難い場合」など、慎重で難しい対応が求められることは確かですが、検討をサボる理由にはしてはいけません。
もう一つ、ハラスメント対応の難しさは、専門家自身が受けてきた教育や慣習に価値観が左右されてしまいがちなところだとも感じます。
例えば私の世代では、学校で教師から叩かれることがまだありましたし、運動部では根性論みたいなのも残っていました。
就職後も、上司の言うことは基本絶対で、職場の先輩の誘いは断れない、という環境でした。
女性の容姿や体型、結婚しているか子どもがいるかで失礼なことを言われても、目くじらを立てるほうがおかしいという風潮でした。
たぶん今20代の方とは、感受性が違うと思います。(今のほうがよくなっているという意味で)
なのでうっかり「自分のころはそのくらい許容範囲だった」とか、相手の悩みを矮小化してしまわないように気を付けています。
少し前のNHK朝の連続テレビ小説「虎に翼」で、時代を先どっていたつもりの女性主人公が、定年退職する上司から「君もいつかは古くなる」と諭されていたシーンを、最近よく思い出します。
もしかしたら下の世代の方たちが考えていることは、本当には分かってあげられないかもしれません。
私達が、自分より上の世代に「分かってもらえてないな」「伝わらないな」と感じていたように。
それでも、レッテル貼りや思い込みはなるべく排除し、想像力を働かせて、丁寧な対応を心がけたいですね。
専門家として知識のアップデートは当然として、感受性もアップデートしなくてはいけないと、常に肝に銘じています。
————————-
とくほ社会保険労務士事務所では、
①初めて人を雇うお客様
②これから人を雇うご予定のお客様
③人事労務に悩む小規模事業所様
を歓迎します
約20年の人事労務経験を持つ社労士が、
採用時の手続きから労働条件の設定、就業規則の作成まで、
安心して進められるようきめ細やかなサポートをお約束します。
全ての業務はプロの社労士が直接対応し、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。
女性の社労士による丁寧な対応で、小さな会社だからこそ必要な、労務サポートをお届けします。
初回相談(Zoom)は30分無料。
メールであれば3往復まで無料です。
ぜひご検討ください
※原則としてオンライン対応のみとさせていただいており
訪問相談、電話相談は対応しておりません。