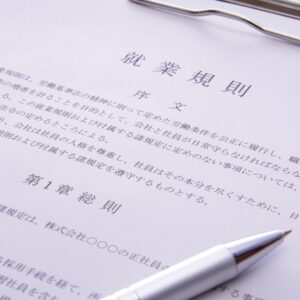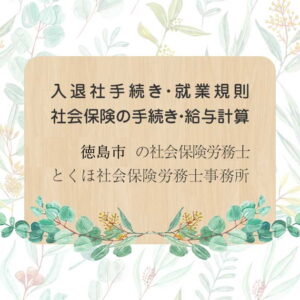私の「人事労務経験」の始まりは、20代の頃、40名規模の商社でした。
経理と労務の兼任…というか、メインは経理でした。
前任者は「労務なんて片手間ですよ」と軽く言っていたくらいで、体系的な引き継ぎはありませんでした。
「任意継続被保険者」や「法定労働時間」のような専門用語は周りも誰も知らず、正解がわからないまま手続きをこなしていました。
「小さな会社の人事」みたいな本を買っても、現場でどう使うのか理解できませんでした。
いま振り返ると、あの混乱や不安は「私だけの問題」ではなく、小規模企業で人事・労務を兼務する担当者がつまずきやすい典型例だったと感じています。
当時の経験をもとに「小さな会社ほど起こりやすい労務トラブル」と「改善のヒント」をまとめました。
もし今、同じように悩んでいる方がいたら、少しでも参考になれば嬉しいです。
「労務は片手間」「引き継ぎもマニュアルもほとんどなし」の問題
小規模企業では、落ち着いた引き継ぎを受けられないことが珍しくありません。
・任意継続や標準報酬月額など、複雑な制度をいきなり扱う
・専門書を買って読んでも、現場でいつ、どう使うかわからない
・「教わっていないから知らない」が、責められる
人事労務はなめてはいけません。専門家になった今だから、そう言えます。
本来であれば時間をかけて理解すべきテーマを、担当者が1人で抱え込んでしまう構造に無理があります。
▶今なら分かる、改善のヒント
・手続きを体系的に整理したチェックリストを作る
・「担当者が理解できる言葉」で教えてくれる外部専門家を活用する
手続きの抜け漏れが起きる
社内の誰も社会保険手続きの正解を知らず、自分自身の知識があいまいなまま進めているのですから、どうしても漏れが出ます。
・退職者の社会保険料を引き忘れた、というかルールを知らなかった
・「固定的賃金」の概念が理解できず、標準報酬の改定を間違えた
・扶養家族の確認が不十分で遡及処理が生じた
どれもよくあるミスではありますが、一つ理解するとまた別の問題が起きるし、年金事務所や従業員には迷惑のかけ通しで、しょっちゅう頭を抱えていました。
▶今なら分かる、改善のヒント
・年次イベント(算定・月変・労働保険年度更新)をスケジュール化
・心配な部分だけでも、社労士などによる確認を導入する
私が今、初めて人を雇うような小規模事業所のサポートを積極的に行っているのは、この頃の苦い経験があるからです。
ちょっと聞ける人がいれば、ぜんぜん違ったと思いますから。言ってみれば「20年前の自分」に向けてサポートしているのです。
給与計算のグレーゾーンが放置される
給与計算は「グレーなまま進んでいるケース」が特に多い分野です。
・「営業手当」に残業代を含めているが、全員一律の金額で就業規則に計算根拠がない
・そもそも私が担当するまで営業担当のタイムカードを回収していなかった
・残業代を1分単位で計算していない
(注)20年前の話なので、今は流石に改善されていると思います。
担当者としては「違法かどうかも判断しづらい」状況で板挟みになります。
▶今なら分かる、改善のヒント
・固定残業代は「金額の根拠」と「超過分の扱い」を明確化
・全員分の勤怠を揃え、実態を見える化する
・「説明できる給与計算」を目指す徳島市のとくほ社会保険労務士事務所・入退社手続き・就業規則・社会保険の手続き・給与計算をサポートのイメージ
就業規則や社内ルールが形骸化している
これは小規模企業に本当に多い問題です。
・労働条件通知書を渡していない
・遅刻・早退・欠勤控除のルールがなく場当たり的に上司が決める
・就業規則は労働基準監督署に提出した「初版」のまま何年も更新されていない
・36協定も数年前の書類が1枚残っているだけ
ルールがない会社では、トラブルが起こるたびに「その場の判断」に頼るしかなく、担当者が疲弊します。
▶今なら分かる、改善のヒント
まず「現状のルール」を棚卸し
・必要最低限からでいいので、実態に合うよう改訂
・就業規則は「会社の健康診断」のつもりで毎年チェック
・36協定など有効期限のあるものは期限を守って提出する
社労士の勉強をしていくうちに「うちの会社ヤバいな」ということが分かってきたので、一つ一つ改善していきました。
ところがそこは「労務は片手間」な会社。「法的に必要です」といっても「なんでそんなことしなきゃいけないの」と、経営陣や管理職に説明しなくてはならず、当時の私は、あまりにも力不足でなかなか上手くいかないこともたくさんありました。
健康管理やコンプライアンス意識が希薄
・健康診断は「受けたいひとが勝手に受ける」運用。40代〜60代で内臓疾患による死亡が複数出た
・社会保険隠し、謎の現金給付など、グレーを越えた行為が行われていた
再三申し上げますが、20年前のことですし、経営陣も変わっているので、もう改善されていると思います。
特に「コンプライアンス違反」は、当時ですら、もし発覚したら会社も厳しい処分を受けていたと思います。
ただ、私がいた会社だけ異常に違法行為が蔓延していたわけではない、と思いたいです。
SNSなどが盛んでなかった20年前は、これだけ問題だらけの会社でも経営陣は「何が悪いのかわからない」「税務署や社会保険事務所を出し抜くのはテクニック」「文句を言う社員がいたら空気を読まないそいつがおかしい」という認識でした。
誤解しないでいただきたいのですが、誰一人「悪い人たち」ではなく、基本良い人たちなんです。昭和を引きずっていて「コンプライアンス」という言葉が辞書になかったというか「労働法やら安全管理よりも、売上が大事。売上ないと会社が潰れちゃうんだから」という価値観で、誰一人それを疑っていなかった。そういう会社だったのです。
担当者として危機感があっても、当時は社労士資格もない、20代のペイペイ社員。「どこから説明すればいいのか」「そもそも話を聞いてもらえない」という現実もあり、自分の無力感を痛感していました。
▶今なら分かる、改善のヒント
・労務は「コスト」ではなく「リスク管理」だと会社に伝える
・最初から大改革を狙わず、まずは法定義務の確実な履行から
・外部チェックを入れることで、担当者ひとりに責任が集中する構造を避ける
おわりに ― 「片手間の労務」から抜け出すために
当時の私は、一人で「これで合ってるのかな」「間違えてないかな」「これは違法なのでは…」と不安に押しつぶされていました。
でも今の自分なら、法的根拠、リスクや判例も踏まえて、ガシガシと社内を改革できたかなあと思います。
小さな会社では、人事や労務を専任で置けないことが普通です。コンプライアンス意識のある経営者や担当者が一人で全部を抱え込むと、心身の負担も、会社のリスクも大きくなります。正しいルールづくりができれば、会社も従業員も、そして担当者自身も驚くほどラクになります。
もし、
「どこから手をつけたらいいかわからない」「うちも同じ状況かも…」
と思うところがあれば、一度ご相談ください。
あなたの会社に合った「現実的な改善の一歩」のお役に立てたら幸いです。
————————-
とくほ社会保険労務士事務所では、
①初めて人を雇うお客様
②これから人を雇うご予定のお客様
③人事労務に悩む小規模事業所様
を歓迎します
約20年の人事労務経験を持つ社労士が、
採用時の手続きから労働条件の設定、就業規則の作成まで、
安心して進められるようきめ細やかなサポートをお約束します。
全ての業務はプロの社労士が直接対応し、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。
女性の社労士による丁寧な対応で、小さな会社だからこそ必要な、労務サポートをお届けします。
初回相談(Zoom)は30分無料。
メールであれば3往復まで無料です。
ぜひご検討ください
※原則としてオンライン対応のみとさせていただいており
訪問相談、電話相談は対応しておりません。