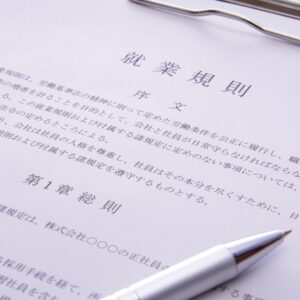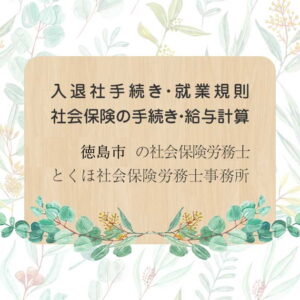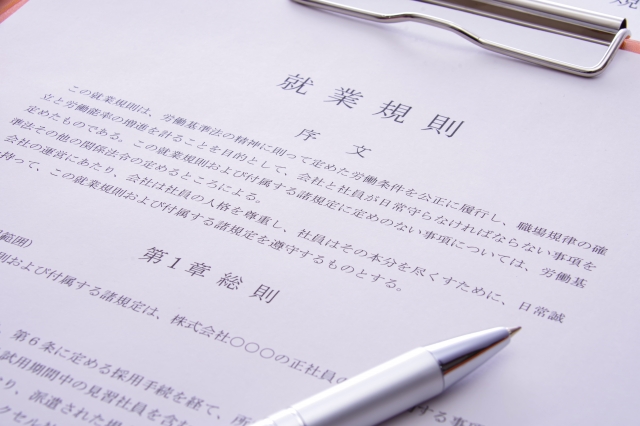

従業員が体調を崩して長期で休む必要がきたとき、就業規則のない会社の経営者の方は「じゃあしばらく休んでいいよ」とあいまいに対応してしまいがちです。
ところが、その後も療養が長引くと、会社はいつまで待てばよいのか、復職の打診をするのか、残念ながら退職してもらうのか「根拠がない」ので計画を立てることができません。
休んでいる従業員も、いつまで休めるのか、休んでいたらどうなるのか、先の見通しがなく不安を感じますし、急に「治らないなら退職」と言われても困ってしまいます。
従業員が6ヶ月私傷病で休んでいます。
そろそろ復職してほしいのですが、どうも様子がわかりません。
まだ時間がかかるようなら、会社としてはいつまでも待つのが難しいので退職させることはできますか?
休職規定はなく、休職命令の文書も出してません。
■ 休職とは
休職は、私傷病で回復まで時間がかかる従業員に、治療に専念するために「会社が命令して」休ませることです。
あくまで会社の命令であり、単に休み続けていれば休職になるわけではありません。
また、従業員には、労働契約に基づいて労務を提供する義務がありますが、治療のためにそれが行えません。
では、会社はいつまでなら待っていられるか?という「解雇猶予」の意味合いもあります。
■ 休職規定がないと復職を打診することができない
休職の「期間」が就業規則に定められていなければ、いつまで経っても「そろそろ復職を」と声をかけることができません。
働くことができない従業員にも、健康保険料や厚生年金保険料は発生します。
「治るまで待って」と言われたまま数ヶ月、果ては年単位に及んでしまうと、業務運営に支障が出ます。
■ 退職を提案することも難しい
休職規定があれば「休職期間満了=自然退職」と定めておくことで、従業員と会社双方が納得して区切りをつけることができます。
ところが、休職規定がなければ「なぜ自分が辞めさせられるのか」「Aさんは待ってもらえたのに、自分は辞めさせられるのか」などと主張され、トラブルに発展する恐れがあります。
■ 他の従業員への説明にも苦慮する
「○○さんは長期で休んでいるのに、なぜ籍を置いたままにしているのか?」
「なぜ特別扱いなのか?」
規定がなければ、休職者以外の従業員に対して公平な説明ができず、不満や不信感を招くことになります。
休んでいる従業員のフォローで先が見えない状態で、職場の雰囲気が悪化することも大きなリスクです。
■ 休職規定で定める事項
・休職を発令する条件(例:私傷病による欠勤が1ヶ月続いたときなど)
・休職期間の上限(例:勤続年数に応じて3ヶ月〜1年など)
・休職中の連絡(仕事の連絡ではなく、療養の経過や復職の見通しなど)
・復職時の手続き(主治医の診断書、産業医の意見、会社から主治医に意見を求める場合の内容など)
・休職期間満了後の取り扱い(自然退職とするかどうか)
これらをあらかじめ定めておくことで、会社も従業員も、万が一のときに安心して対応することができます。
■ まとめ
私傷病休職は会社からの命令により発生します。
休職規定がない会社は、従業員に配慮しているようでいて、実は会社も従業員も守れていません。
「休んでいいよ」と言ったあとに身動きが取れなくなる前に、休職規定を整備しておくことが、会社を守り、従業員を支えるための第一歩になります。
————————-
とくほ社会保険労務士事務所では、
①初めて人を雇うお客様
②これから人を雇うご予定のお客様
③人事労務に悩む小規模事業所様
を歓迎します
約20年の人事労務経験を持つ社労士が、
採用時の手続きから労働条件の設定、就業規則の作成まで、
安心して進められるようきめ細やかなサポートをお約束します。
全ての業務はプロの社労士が直接対応し、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。
女性の社労士による丁寧な対応で、小さな会社だからこそ必要な、労務サポートをお届けします。
サービス内容はこちら
初回相談(Zoom)は30分無料。
メールであれば3往復まで無料です。
ぜひご検討ください
※原則としてオンライン対応のみとさせていただいており
訪問相談、電話相談は対応しておりません。