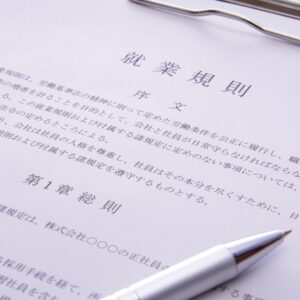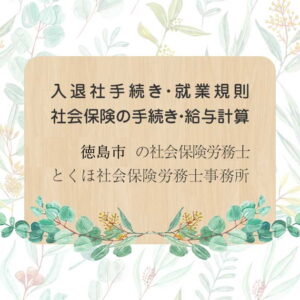6月、7月は夏のボーナスシーズンですね。
健康保険・厚生年金保険に入っている事業所が「賞与」を支給する場合は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)控除・納付の手続きが必要になります。
月々の給与と同様に、会社は適切に保険料を控除し、手続きを行う必要があるのです。
今回は、賞与支給時の社会保険料の計算方法と手続き、注意点について簡単にまとめます。
「賞与」の定義
健康保険・厚生保険における「賞与」は、
賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものをいいます。
例えば、3ヶ月を超える期間ごとに支給される「インセンティブ」年末年始稼働したことに対する「越年手当」なども賞与の対象になります。
ただし、同じ「インセンティブ」という名称でも年4回以上支給されるものは「標準報酬月額」の対象となります。
逆に、年3回以下の支給であっても、労働の対償ではない結婚祝金等は「賞与」対象外です。
賞与の社会保険料の計算方法
賞与に対する社会保険料は、【標準賞与額 × 保険料率】で計算します。
標準賞与額とは?
税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額が「標準賞与額」となります。
賞与額 556,220円→ 標準賞与額 556,000円
また、賞与の保険料には上限額があります。
健康保険:年度の累計額573万円
厚生年金保険:1ヶ月あたり150万円
上限を超える場合は、それぞれの上限額までで保険料を計算します。

徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所の給与計算
提出が必要な書類
賞与を支給した際には、次の書類を提出します。
また、標準賞与額の年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)を超える場合は、被保険者からの申し出に基づいて次の届書が必要です。
・健康保険 標準賞与額累計申出書
賞与保険料の控除で注意したいポイント
賞与支給月の退職者のうち、月末以外に退職されるかたについては社会保険料控除の際に注意が必要です。
月の途中に退職したり死亡退職された方の賞与からは、健康保険料・厚生年金保険料の控除は行いません。
こういった方の賞与からは、健康保険料・厚生年金保険料は控除しません
賞与支払時に退職日がわかっている場合は、あらかじめ賞与から保険料控除されないように確認しておきましょう。
賞与支払時に退職の情報が来ていなかったり、賞与支給から月末前までの間に死亡した場合は「後日」控除した保険料の返金が必要になります。
健康保険料・厚生年金保険料を控除
その後、7月30日までに退職、または亡くなられた場合
→ 退職者やご遺族に、控除した保険料の返金が必要になるということです
賞与支給月に、月末以外の退職があったときは保険料に注意、と覚えておきましょう。
従業員の死亡や急な退職、解雇などは、それだけでも手続きが多く、人事労務担当としては焦ってしまいますよね。
賞与の保険料のことも思い出して、退職手続きと同時に、説明・処理ができると二度手間を避けられます。
失念して何ヶ月も経ってから気が付き、退職者やご遺族に連絡するのは、返金させていただくとはいえ気まずいものです・・・。
まとめ
賞与支給時の社会保険料は、給与と同様に適切な計算・控除・手続きが求められます。
正しい手続きで従業員・会社双方にとってスムーズな運用を目指しましょう。
参考: 年金事務所のサイト
————————-
とくほ社会保険労務士事務所では、
①初めて人を雇うお客様
②これから人を雇うご予定のお客様
③人事労務に悩む小規模事業所様
を歓迎します
約20年の人事労務経験を持つ社労士が、
採用時の手続きから労働条件の設定、就業規則の作成まで、
安心して進められるようきめ細やかなサポートをお約束します。
全ての業務はプロの社労士が直接対応し、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。
女性の社労士による丁寧な対応で、小さな会社だからこそ必要な、労務サポートをお届けします。
初回相談は1時間無料。
メールであれば3往復まで無料です。
お伺いできる範囲であれば対面でも、Zoomなどオンラインでも承ります。
ぜひご検討ください